 企画B-2トップに戻る
企画B-2トップに戻る
 企画B-2トップに戻る
企画B-2トップに戻る
- PART1
12月20日、企画制作研修のヤマ場の一つともいえる、映像撮影・録音のプロセスを体験した。場所は東京音楽大学の中目黒・代官山キャンパスにあるTCMホール。2019年に完成したばかりの真新しい会場だ。
演目は、受講生5人の立案した企画をもとに、伝統曲「さくらさくら」を箏奏者・作曲家の本間貴士氏に編曲していただいた「さくら狂詩曲」。演奏者は、受講生のうち箏やピアノ、フルートを演奏する3人(有馬美梨さん、木ノ瀬佳子さん、島多璃音さん)と、今回の講師をされている滝田美智子先生(箏曲演奏家・東京音楽大学大学院客員教授)、そして本間氏にも箏と三味線で加わっていただいた。構成台本は、ディレクターを務めた受講生の島多さんが作った。
受講生5人は当日、午前9時に会場に集合。映像制作のプロで、やはり今回の講師でもある姫田蘭先生(映像制作ディレクター/カメラマン・民族文化映像研究所理事)の仕切りによって舞台設営が進んでいく様子を学ぶ。

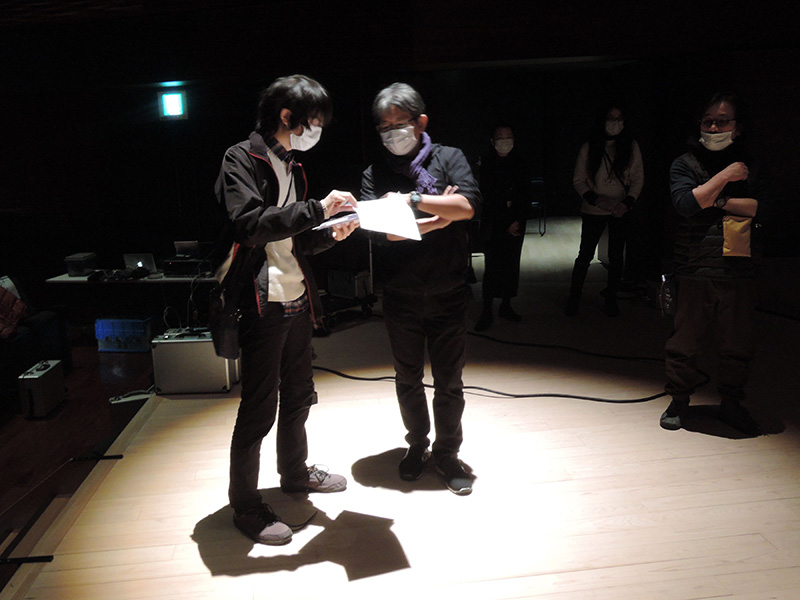
 集合直後の打ち合わせ
集合直後の打ち合わせ

 楽器や照明のセッティング
楽器や照明のセッティング - PART 2
6つのパートで構成する曲のうち、楽器編成が大きなパートから順番に、リハーサルと本番を進めていく。最初のパートは1時間以上かけて、何度も撮り直すことに。2つのパートを撮り終え、午後1時を回ったところで昼食の休憩に入る。
再開後は、息も合って次第にペースが上がっていった。用いた楽器は、箏が13絃から25絃までの3面、それに三味線とピアノで、楽器によって音量に差がある。パートによって異なる楽器編成に合わせ、最適なバランスにするために舞台上の各楽器の位置や、互いの距離を微調整する必要がある。また、舞台照明の色をパートによって変えるため、その調整も欠かせない。これらの作業を繰り返しながら、収録が進む。そして午後4時半前に収録完了。5時までに完全撤収することができた。
収録の合間に講師の先生方や本間氏に、受講生の企画に対する感想を伺ったところ、収録までのプロセスにおけるコミュニケーションに改善の余地がある、とのご指摘をいただいた。たしかに受講生同士の話し合いが、限られた時間の中で、オンラインだけでは十分に尽くすことができず、ぶっつけ本番のようになってしまった部分があることは否めない。今後は同様の環境下で企画やマネジメントをせざるを得ない場面もありそうなので、とても良い勉強になった。
(文・写真:古河 美保、真部 保良)







 パートごとのリハーサルと本番
パートごとのリハーサルと本番


