Ⅰ.基礎講座
(各講座の動画尺は約1時間です)
1. 現代舞台講座・・・2020年8月8日(土)10時より動画を配信します(動画配信期間:2021年2月末3月31日(水)まで)
文化施設における現代的な演出・舞台技術やプログラムの展開を学びます。
- 動画配信は終了しました
- 視聴お申し込みを締め切りました
伝統を踏まえた邦楽公演の新しい見せ方
- 町田龍一
- <公益財団法人 日本製鉄文化財団(紀尾井ホール)前常務理事>
- 1952年福岡県生。九州大学法学部を経て、新日本製鐵(現日本製鉄)に入社。その後同社の運営する日本製鉄文化財団(紀尾井ホール)でホール貸し、総務、洋楽・邦楽の制作等運営全般に従事。海外関連としてオーケストラの欧州音楽祭、日米桜寄贈100周年記念公演等への参加、邦楽では韓国、欧州において浄瑠璃・歌舞伎舞踊公演等を企画実行。他に東京芸術大学演奏芸術センター前評議員会長、江戸東京博物館ホール利用選考委員長など。
公立ホールにおける邦楽公演の実例
- 本田恵介
- <公益財団法人 熊本県立劇場 理事 / 参与>
- 1982年、(財)熊本県立劇場採用。アジアユースオーケストラのミュージックキャンプ運営、ローマ弦楽合奏団ほか海外演奏団体の招聘・ツアー随行など音楽事業を中心に担当。その後、舞台制作者養成、アウトリーチ事業の普及を積極的に展開。2005年から(財)地域創造の公共ホール音楽活性化事業や邦楽地域活性化事業のコーディネーターを務めた。現在、(公社)全国公立文化施設協会理事、専門委員会委員長、支援員を務めている。
地域に根差す劇場の伝統芸能支援
~継承と創造~
- 木原義博
- <島根県芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場 館長>
- 1962年島根県益田市(旧美都町)出身。幼少期より島根県石見地方の伝統芸能「石見神楽」(2019年5月 日本遺産認定)に慣れ親しむ。大学卒業後、民間企業に勤務したのち、島根県発の創作ミュージカルとの出会いをきっかけに、益田市の文化ホールに転職。文化保存伝承事業「みとの神楽」を企画し、廃れた演目の掘り起こしを行う。2005年、島根県芸術文化センター「グラントワ」開館時より劇場部門文化事業課に勤務。以後「石見の夜神楽定期公演」「しまね子ども神楽フェスティバル」「須佐之男命の軌跡 岩戸・大蛇」「神楽ボ レロ」など、数多くの伝統芸能の保存・伝承・交流事業に取り組む。2019年4月より同センター いわみ芸術劇場 館長。
舞台の撮影・これからの時代の動画配信
- 姫田蘭
- <映像制作ディレクター / カメラマン・一般社団法人民族文化映像研究所 理事>
- 1965年、東京生まれ。学生時代より記録映画・CM等の音楽制作で活動。2000年頃より映像制作をはじめ、現在はコンサートや演劇の舞台収録を主に、ビデオ・写真の撮影、演出を行っている。一般社団法人民族文化映像研究所理事、「映像のまち・かわさき」推進フォーラム理事。
2. 現代運営講座・・・2020年8月8日(土)10時より動画を配信します(動画配信期間:2021年2月末3月31日(水)まで)
現代社会において求められる機能を理解し、それに即した多様な運営体制の構築を学びます。
- 動画配信は終了しました
- 視聴お申し込みを締め切りました
創造的な復興と地域フェスティバルの設計図
~現代の視点で芸能の魅力を引き出すために~
- 坂田雄平
- <宮古市民文化会館 館長補佐 / プロデューサー>
- NPO法人いわてアートサポートセンターにて文化施設の運営、アートプロジェクトや芸術祭の企画・運営に携わる。その他、岩手県文化芸術コーディネーター(沿岸地区)、(一財)地域創造「公共ホール現代ダンス活性化事業」コーディネーター等を務める。2003年より桜美林大学舞台芸術研究所のチーフ、07年より財団法人地域創造、12年より17年まで、北九州芸術劇場にて舞台芸術フェスティバルや領域横断型プロジェクト等を行う。
文化をつなぐ博物館
~墓場からステージへ~ 浜松市楽器博物館の実践
※この講座は、8月22日から動画配信予定です
- 嶋和彦
- <浜松市楽器博物館 前館長>
- 京都大学教育学部卒業。リコーダーと民族音楽を大阪音楽大学西岡信雄教授に師事。全日本リコーダーコンクールアンサンブル部門最優秀賞、大阪文化祭賞等受賞。ロンドン他海外でも公演。94年楽器博物館開設準備に従事。95年開館より学芸員、04年から18年まで館長。多彩な活動を展開し博物館を12年度文化庁芸術祭レコード部門大賞、14年度小泉文夫音楽賞に導く。国際博物館会議ICOM2019京都大会運営委員・楽器博物館国際委員会担当。
国立民族学博物館における芸能の映像記録作成と活用
- 福岡正太
- <国立民族学博物館 教授>
- 国立民族学博物館人類基礎理論研究部教授。民族音楽学専攻。東南アジア、特にインドネシアの伝統音楽を研究。現代における伝統音楽の継承、発展の過程とラジオやレコードとの関わりや、無形文化遺産の映像記録の諸問題について関心をもっている。共著に『東南アジアのポピュラーカルチャー』(スタイルノート、2018)、『民族音楽学12の視点』(音楽之友社、2016)、『インドネシア芸能への招待』(東京堂出版、2010)など。
「舞台公演」と著作権について
ー実演家の権利を中心にー
- 君塚陽介
- <公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター(CPRA) 著作隣接権総合研究所 法制広報部>
- 1976年東京都町田市生まれ。1998年青山学院大学法学部私法学科卒業、2001年同大学院法学研究科博士前期課程修了。2002年日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)入社、現在に至る。主に実演家の権利保護に関する著作権法の調査研究業務などに従事している。
3. 創作表現講座・・・2020年8月22日(土)10時より動画を配信します(動画配信期間:2021年2月末3月31日(水)まで)
伝統音楽を素材にした現代的な創作や演奏の事例や技法について学びます。
- 動画配信は終了しました
- 視聴お申し込みを締め切りました
ジャワガムラン創作
〜現地・海外・東京の事例紹介〜
※この講座は、8月8日から動画配信予定です
- 樋口なみ
- <ガムラン奏者・本学講師>
- 東京音楽大学在籍中にガムランと出会い、ジャワと日本を往復しながら研鑽を積む。1998年より2007年まで東京音楽大学付属民族音楽研究所研究員として勤務。2008年よりNPO法人日本ガムラン音楽振興会(東京都)理事。2011年より東京音楽大学ガムラン講師として学部授業および社会人講座、大学院の個人レッスンカリキュラムのガムラン実技を担当しながら演奏活動を続けている。インドネシア大使館等での演奏、学校のガムランコンサート、海外公演など出演多数。
能と現代音楽
※この講座は、8月8日から動画配信予定です

Photo:Hiroaki Seo
- 青木涼子
- <能声楽家>
- 世界の主要な現代音楽の作曲家と共に、能の声楽である「謡」を素材にした新しい楽曲を発表、国内外でオーケストラとの共演、オペラ出演を行っている。東京藝術大学音楽研究科修士課程修了(能楽観世流シテ方専攻)。ロンドン大学博士課程修了。平成27年度文化庁文化交流使。第11回「創造する伝統賞」受賞。
箏によるさまざまな音楽活動
~アウトリーチや洋楽器とのコラボレーションを通して
- 片岡リサ
- <箏奏者・大阪音楽大学特任准教授>
- 大阪音楽大学卒業、大阪大学大学院文学研究科修了。幼少より箏・三絃を始め、数々のコンクールで第1位を受賞。平成13年度文化庁芸術祭新人賞を洋楽邦楽問わず史上最年少で受賞するなど、伝統音楽の枠を超えた音楽性が様々なジャンルで高く評価されている。第21回出光音楽賞、平成22年度大阪文化祭賞、平成23年度咲くやこの花賞、平成30年度文化庁芸術祭優秀賞など受賞。現在、大阪音楽大学特任准教授、同志社女子大学・兵庫教育大学講師、京都市立芸術大学伝統音楽研究センター共同研究員。
対象
- 文化行政・文化施設職員
- 伝統音楽・伝統芸能団体関係者
- 学校教育関係者
- アートマネジメントに従事している者、またはそれを志す者
定員
なし
- オンライン(オンデマンド配信)で実施するため定員はありません。
申し込み期限
- 動画視聴後、講師への質問(メール)をされたい方:
2020年 8月 20日(木)まで
(質問票の締め切りは8月26日まで、9月上旬頃に講師からの回答を送らせていただきます。)
- 動画視聴のみの方(講師への質問をされない方):
2021年 1月 28日(木)まで
ご注意
- 動画は配信期間内であればいつでも視聴できます。
(2021年2月末3月31日(水)まで)
- 動画視聴方法等については、お申し込みをいただいてから追ってご連絡させていただきます。(こちらからの連絡は、土日祝日及び8月11日(火)~14日(金)、12月25日(金)~2021年1月6日(水)以外の日になります)



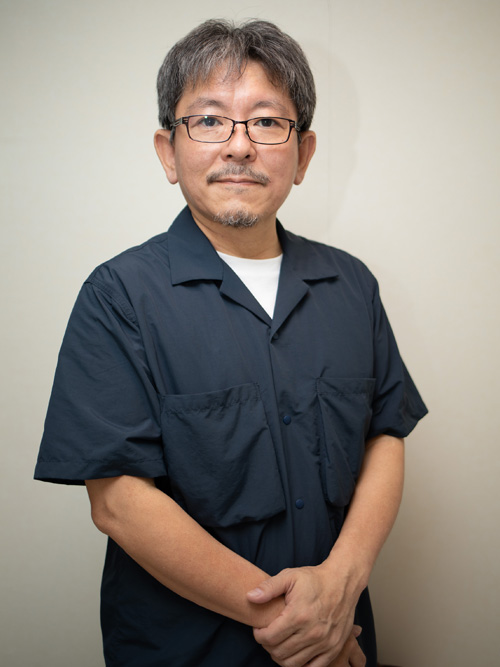








 Photo:Hiroaki Seo
Photo:Hiroaki Seo