



音楽教育研究領域では、音楽科教員育成の枠組みにとらわれず、多様な音楽教育の場及び音楽活動の場を想定して、音楽と社会と人間との関わりについての研究を行なっています。教員の専門が音楽教育のみならず、文化政策、民族音楽、心理学、社会学と幅広いのも特徴です。このような学際的な研究環境で、互いに影響を受けながらテーマを決め、研究を深める2年間を過ごすことができます。また学問的な研究とともに、選択で実技の履修ができ、個人レッスンを通して実技の能力を高めることもできます。
学生の専門も様々で、研究テーマも多種多様です。音楽教師としての経験を論文にまとめようと入学してくる社会人や、日本と母国との音楽教育や文化の比較研究を行なっている留学生もいます。修了後は、教員をはじめ、音楽出版社、音楽ホールなどに就職し、自らの個性を生かしながら社会で活躍しています。
音楽学は、音楽について学問的に調べ、言葉によって論ずる分野です。本学の修士課程音楽学研究領域では、学部で演奏を専攻してきた学生や他大学出身の学生など、幅広い出自の学生が学んでいます。多様なテーマでの研究が可能であり、情報化の進んだ現在、かなりの研究活動を大学をベースとして行い、在学中に短期間国内や海外に出て資料収集・調査等を行う学生も増えています。
どのような研究テーマを選ぶとしても、音楽学研究領域で身に着けられる調査・考察・文章化・プレゼンテーションの能力は、修了後に多様な分野で生かすことができます。優秀な修士論文には、修了後に日本音楽学会で要旨発表の機会が与えられます。また、これまでの修了者の具体的な進路として、研究機関や図書館(在学中に司書資格取得の上で)、あるいは出版社、文化施設、一般企業が挙げられます。また、博士後期課程でさらに研鑚を積むことも可能です。
音楽と社会を結びつける人材として、音楽学研究領域で学んでみませんか?
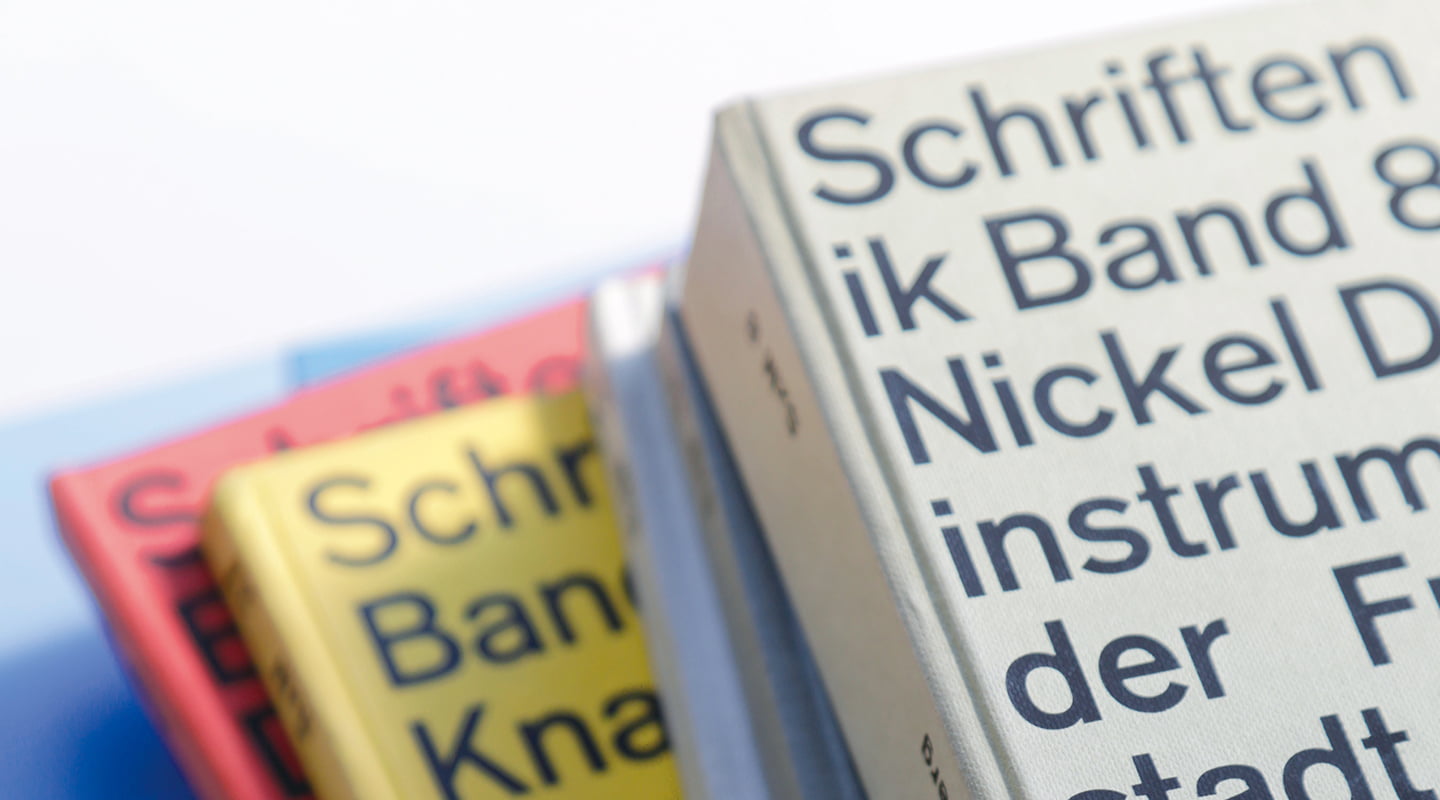

ソルフェージュ研究領域では、自身の実技演奏、研究などに役立つ楽曲の総合的理解、把握、解釈を可能にする高度な読譜力の習得を目指します。具体的な内容は、初見、移調、スコアリーディング等を中心としたソルフェージュ実技の習得、和声学、対位法の習得、また多面的、実践的な楽曲分析と音楽様式の変遷への考察等です。各自の専門実技のさらなる習得に加えて、論文作成およびソルフェージュ課題の作成を行います。社会の様々な場において、多様な音楽活動を展開できる人材を養成しています。
音楽分野において有効なPC活用の習得とともに、将来を見据えたオンラインを含む教育研究の1つとして、配信のためのソルフェージュ授業動画を作成し、教材研究をしています。
修了後は、音楽高校、一般高校の教諭、講師として勤務するほか、音楽大学及びその付属音楽教室の講師として指導にあたっています。
多文化音楽研究領域は、多様な文化や民族性を背景とした世界観のもとに育まれてきた世界各地の伝統的な音楽文化を、現代社会における文化の多様性の視点から探求し、新たな音楽文化を創造し、発信していくことをめざす研究領域です。
日本を含む世界各地の伝統音楽を専門に研究する者が、互いの専門研究領域を学び合うことで、新しい音楽文化を創り出していきます。
●修士研究
修士研究は、3つの方向から選ぶことができます。
○理論研究:多文化の音楽文化を研究し、論文を執筆する。
○開発研究:多文化の音楽を現代社会に生かす企画・制作・プロデュースなどを開発する。
○演奏・創作研究:多文化の伝統と現代をクロスさせながら新しい演奏や新しい作品を創造する。
●教育内容
多彩な授業科目の中から、各自の修士研究の内容や方向に合わせて、理論と実技を自在に組み合わせながら学んでいきます。
・音楽文化研究としての日本音楽や民族音楽の講義や演習【多文化音楽研究演習1】
・アートマネージメントやメディア演習、作品制作のための演習【多文化音楽研究演習2】
・日本音楽を含む世界各地の伝統音楽の実技レッスン【多文化音楽実技実習】
*「多文化音楽実技実習」履修可能楽器
アイヌ伝統音楽(トンコリほか)
中国音楽(二胡、古筝、古琴、笛子)
キルギス音楽(コムズほか)
モンゴル音楽(馬頭琴ほか)
インド音楽(シタール)
インドネシア音楽 (ジャワガムラン、ジャワ舞踊)
邦楽 (箏、尺八、三味線ほか)
*多文化音楽研究領域のウェブサイトはこちら


吹奏楽は多様な表現の可能性を持つ音楽の一形態であると同時に、様々な形で社会との関わり方を持つものでもあります。吹奏楽研究領域では、学生一人ひとりがそれぞれ演奏法・指導法・歴史・社会との関わり・作編曲法など多種多様な選択肢から研究テーマを定め、それに応じた選択必修科目を履修し研究を行います。テーマによっては個人レッスン形式で専門楽器実技や作編曲の研鑽を積むことができます。また、どの研究テーマにおいても自身が演奏者として合奏に参加することも必修となっており、常に現場的な視点に対する考察が可能となっています。
学位審査としては、どんな研究テーマにおいても修士論文の執筆が必須となります。そのためのゼミにおいては、学生同士が様々な角度から吹奏楽について学び合うことにより、広範な見識を修得することになります。ほか、研究テーマによっては修士論文に加え、修士演奏の実施または修士作品の提出が必要となります。