

東京音楽大学は、コンサルティングファームのデロイト トーマツグループと共同で、クラシック音楽を通じてビジネススキルを磨く講座『クラシック音楽で紡ぐこれからのビジネススキル』を社会人の方々を対象に開講します。
講義に加え、生演奏の視聴や伝統楽器の演奏を通して、新たな視点から洞察力、創造力、表現力などを磨きます。
※お申し込みは終了いたしました。
講師:藤田茂教授(音楽学)
演奏:安田正昭特任教授(ピアノ)
楽曲:オリヴィエ・メシアン(1908-1992) 「鳥のカタログ」第2巻「カオグロヒタキ」
場所:TCMホール(中目黒・代官山キャンパス)

学位等:博士(音楽学)(東京芸術大学)、DEA (musicologie)(Université de Paris 4, Sorbonne)
フランス政府給費留学生としてソルボンヌ大学に学んだあと、東京芸術大学で博士号を取得。主な研究領域は19世紀・20世紀のフランス語圏の音楽と音楽文化史。ブリュッセル王立音楽院等では、短期招聘も務める。メシアン論・デュティユー論をはじめとする専門的な論文のほか、国内外のオーケストラ公演の曲目解説を定期的に寄稿している。ヒル&シメオネ『伝記 オリヴィエ・メシアン』(音楽之友社)訳者。
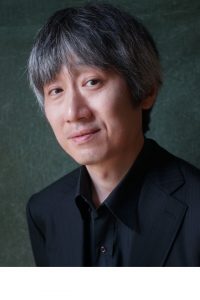
1967年東京生まれ。5歳よりピアノを始める。
東京藝術大学附属音楽高等学校在学中にスペイン・バルセロナで行われた第30回マリア・カナルス国際音楽コンクール・ピアノジュニア部門で優勝。藝大を中退してパリ国立高等音楽院に留学。大作曲家オリヴィエ・メシアンの夫人であるイヴォンヌ・ロリオに師事。メシアンとも交流を持つ。第1回パリ・スタインウェイ・ピアノコンクール優勝。フランス国際音楽コンクール優勝、モーツァルト賞、メシアン賞を受賞。
その他受賞多数。パリ国立高等音楽院をピアノ、室内楽、伴奏法の全てをプルミエプリ(一等賞)を得て卒業。2003年に帰国。2008年に東京でメシアン生誕100年を記念して連続リサイタルを行い絶賛を博す。
演奏と後進の指導に力を注ぎ2025年4月より東京音楽大学特任教授に就任。
講師:新林一雄准教授(音楽学)
演奏:ドミトリー・フェイギン教授(チェロ)
楽曲:J. S. バッハ:チェロ組曲 第1番 BWV 1007より「前奏曲とジーグ」
演奏:橘高昌男講師(ピアノ)
楽曲:J. ハイドン クラヴィーア・ソナタ変ホ長調Hob XVI 52 より 第1楽章
場所:中目黒・代官山キャンパス

東京芸術大学博士後期課程修了。博士(音楽学)。DAAD 奨学生としてドイツ・ドレスデン工科大学に留学。日本学術振興会特別研究員(PD)として、18世紀ドイツを中心としたオーケストラの研究を行う。これまでに、東京芸術大学、東邦大学、明治学院大学などで非常勤講師を務める。現在、東京音楽大学の音楽文化教育専攻で教鞭を執るほかにも、立教大学、洗足学園音楽大学、クニトInt’lユースオーケストラ附属ソルフェージュクラスで講師を務める。
研究の専門はバロックや古典主義の時代のドイツのオーケストラですが、時代や地域に関係なく、広い音楽の世界をみなさんと話し合えたらと思っています。

モスクワに生まれる。モスクワ音楽院大学院卒業。
在学中からロシア国内外でソロ及び室内楽での演奏活動を始める。
今までにロシア及び日本でのコンクールにて数々の賞を受賞。
2003年に来日、今までに小林研一郎、広上淳一などの指揮者と日本のオーケストラで共演する。
現在東京音楽大学教授。
日本国内外で演奏活動を行っている。
近年ではコンクールの審査員も務める。

東京藝術大学附属音楽高等学校を経て同大学を首席で卒業。
大学在学中に安宅賞を受賞。第65回日本音楽コンクール第1位、合わせて野村賞、井口賞を受賞。イル・ド・フランス国際ピアノコンクール第1位ほか、ロバート・ウィリアム&エーミー・ブラント国際ピアノコンクール第3位(イギリス・バーミンガム)など国内外で入賞を果たす。平成13年度文化庁在外研修員としてジュネーブ音楽院ソリストディプロム課程に入学。ソリストディプロムを取得し卒業後、パリ国立地方音楽院古楽器科フォルテピアノ専攻にて更に研鑽を積む。審査員満場一致最優秀の成績で卒業。ヨーロッパCATV「MEZZO」、NHK「ぴあのピア」「スーパーピアノレッスン」、NHK-FM「名曲リサイタル」に出演。
これまでにピアノを大楽勝美、植田克己、クラウス・シルデ、ドミニク・メルレの各氏に師事、フォルテピアノをパトリック・コーエン氏に師事。
また、東京交響楽団、東京都交響楽団、札幌交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団など数々のオーケストラと共演。また、定期的にフランス・フレーヌ他にてマスタークラスやコンサートに招聘されるなど活発な音楽活動を展開。
現在、武蔵野音楽大学、東京音楽大学で後進の指導にあたっている。
講師:大谷康子教授(管弦楽)
インタビュアー:岡田敦子客員教授
場所:TCMホール(中目黒・代官山キャンパス)

2025年にデビュー50周年を迎え、人気・実力ともに日本を代表するヴァイオリニスト。華のあるステージ、深く温かい演奏で聴衆に感動と喜びを届けており「歌うヴァイオリン」と評される。2025年1月には、サントリーホール大ホールにてデビュー50周年記念演奏会を開催。世界初演のヴァイオリン協奏曲「未来への讃歌」を含む意欲的なプログラムで、満員の聴衆を魅了した。5月にはデビュー50周年記念全国ツアー(ピアノ:イタマール・ゴラン/全14公演)を開催、好評を得る。東京芸術大学、同大学院博士課程修了。在学中よりソロ活動を始め、ウィーン、ローマ、ケルン、ベルリンなどでのリサイタル、トロント音楽祭、ザルツブルグ市などに招待され好評を得る。また、学生時代より東京シティ・フィル首席コンサートマスターを、その後東京交響楽団でソロコンサートマスターを務め、名誉コンサートマスターの称号を授かる。これまでにリサイタルはもとより、N響、モスクワ・フィル、スロヴァキアフィル、シュトゥットガルト室内楽団など国内外の著名なオーケストラと多数共演。また、1公演で4曲のヴァイオリンコンチェルトを1日2公演行うという前代未聞の快挙を達成し話題となった。キーウ(キエフ)国立フィルとは2017年以降毎年招聘されている(情勢により中断)。最新CDはイタマール・ゴランとのフランスのエスプリ薫る珠玉の名曲集。CDは他に、ベストセラー「椿姫ファンタジー」(SONY)や、ベルリンでの録音による「R.シュトラウス/ベートーヴェン・ソナタ№5(ピアノ: イタマール・ゴラン)」(SONY)も評価が高い。その他多数リリース。著書に「ヴァイオリニスト 今日も走る!」(KADOKAWA)がある。BSテレ東(毎週土曜朝8時)「おんがく交差点」では春風亭小朝と司会・演奏を務め、八面六臂の活躍をしている。文化庁「芸術祭大賞」受賞。東京音楽大学教授。元東京芸術大学客員教授。元東京芸大ジュニア・アカデミー特別教授。(公財)練馬区文化振興協会理事長。川崎市市民文化大使。高知県観光特使。(公財)日本交響楽振興財団理事。(公社)日本演奏連盟常任理事。使用楽器はピエトロ・グァルネリ(1708年製)と日本音楽財団より貸与のストラディヴァリウス「ロード・ニューランズ」(1702年製)。
オフィシャル・ホームページ:https://www.yasukoohtani.com
【公式YouTube】「大谷康子のやっこチャンネル」演奏動画続々公開中!

東京芸術大学付属高校、同大学を経て、同大学院博士課程(鍵盤領域)修了。スクリャービン(1872~1914)の演奏と論文によって、同大学の西洋音楽の分野で初めて博士号(学術博士)を取得。日本学術振興会特別研究員、東京芸術大学および沖縄県立芸術大学非常勤講師、京都市立芸術大学助教授を経て、2005年より東京音楽大学教授、2022年より副学長、現在客員教授。
演奏、教育、研究のみならず、評論活動も行い、ショパン没後150年記念国際シンポジウム(ワルシャワ)、スクリャービン生誕125周年記念国際音楽祭(モスクワ)などに招かれ、講演やリサイタルを行なう。
校訂楽譜『スクリャービンピアノ曲全集』(全7巻、春秋社)はモスクワの国立スクリャービン博物館に所蔵されている。
ゲスト講師:梅津時比古(音楽批評)
演奏:杉野正隆特任准教授(バリトン)
演奏:服部容子専任講師(ピアノ)
楽曲:シューベルト:魔王 Op. 1, D. 328、菩提樹 冬の旅 Op. 89, D. 911 – 第5番
場所:C302教室(中目黒・代官山キャンパス)

神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大学文学部西洋哲学科卒。独・ケルン音大で研修。ドイツの出版社・Roderer Verlag よりシューベルト研究の著書が《哲学叢書》として2冊、翻訳刊行されている。今秋から『梅津時比古セレクション(著作集)』全5巻の刊行が始まった。第54回芸術選奨文部科学大臣賞、第19回岩手日報文学賞賢治賞、日本記者クラブ賞、NHK制定「日本の百冊」など受賞。現在、毎日新聞特別編集委員、桐朋学園大学特命教授、早稲田大学招聘研究員。

国立音楽大学声楽科卒業。同大学院修了。JSG国際歌曲コンクール、友愛ドイツ歌曲コンクール入賞。文化庁派遣芸術家在外研修員として一年間、ハンブルグに滞在。「ラインの黄金」「ワルキューレ」ヴォータン役、「ハムレット」タイトルロール等でオペラに出演。「詩人の恋」「冬の旅」等のドイツリートのコンサートを各地で開催。二期会会員。日本カール・レーヴェ協会会員。東京室内歌劇場代表理事。東京音楽大学特任准教授。

桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。
1996年度文化庁在外派遣研修員としてニューヨーク留学。国内外の多数オペラプロダクションに音楽スタッフとして参加。現在リサイタル等で多くの歌手と共演するピアニストとして、また指揮者としても活動中。東京音楽大学専任講師。洗足学園音楽大学客員教授。東京藝術大学大学院、お茶の水女子大学、愛知県立芸術大学、各非常勤講師。日本ドイツリート協会会員。日本声楽家協会理事。
講師:木村佳代(民族音楽研究)
講師:樋口なみ(民族音楽研究)
インタビュアー:藤原豊教授(作曲)
講座補助:横田誠(東京音楽大学音楽文化教育研究員)
場所:B410教室(池袋キャンパス)

東京音楽大学講師。ガムラングループ・ランバンサリ代表。NPO法人日本ガムラン音楽振興会理事。東京芸術大学音楽学部楽理科卒業。在学中よりガムランをサプトノ氏に師事。その後頻繁にインドネシアに通い研鑽を積む。2007年8月~2008年3月インドネシア国立芸術大学ISIスラカルタ校に留学。1997~2001年東京音楽大学民族音楽研究所研究員。2010年より東京音楽大学講師としてガムランを指導。
現在、ガムラン演奏家、指導者として活動中。共著に東京音楽大学付属民族音楽研究所編『ガムラン入門』(スタイルノート)、皆川厚一編『インドネシア芸能への招待』(東京堂出版)

東京音楽大学講師。NPO法人日本ガムラン音楽振興会理事。研究者名は樋口文子。
東京都生まれ。東京音楽大学教育科在学中に佐藤まり子女史にガムランの手ほどきを受けた後、1989年よりガムラングループ・ランバンサリで演奏活動を開始。以後度々ジャワにて、ワキジョ氏、スバント氏ほか数多くの著名な指導者、演奏家に師事。1997~2006年東京音楽大学付属民族音楽研究所研究員、2010年より東京音楽大学講師として学部生、院生の実技授業のほか、生涯教育としてガムラン社会人講座を担当。
現在、ガムラン演奏家、指導者として活動中。共著に東京音楽大学付属民族音楽研究所編『ガムラン入門』(スタイルノート)、制作CDに同研究所協賛『ジャワガムラン・スラカルタ編』(自主制作4枚組チャリティCD)

1982年東京音楽大学音楽学部卒業。1984年同研究科修了。1978年/1979年日本音楽コンクール入賞。1983年イタリア・ヴィオッティ国際音楽コンクール入賞。1985年ポーランド・ヴィニアフスキ国際ヴァイオリンコンクール作曲部門特別賞。1987年イタリア・ブッキ賞国際音楽コンクール第1位。1988年NAA( NewArtistAudition )CBS-SONY/FM東京賞受賞。2019年 第74回文化庁芸術祭 演劇部門(関西)大賞を人形劇団クラルテ公演「女殺油地獄」音楽担当として受賞。
在京各オーケストラの編曲・キーボード奏者を務めるほか、国民文化祭などの演劇作品や各地の市民演劇、ミュージカル作品楽担当、また、石井竜也「D-Dream」コンサートツアーのサウンドプロデューサーやNHK教育TV「お父さんのためのやさしいピアノ塾」のアレンジ企画担当など、ジャンルを問わず作編曲家として、またキーボードプレイヤーとして多岐にわたる活動をしている。
現在 東京音楽大学および大学院教授(作曲)。芸術音楽コースおよびMMC(ミュージック・メディアコース)・ピアノ創作コース、修士課程(作曲芸術、作曲応用、多文化音楽領域など)担当。
東京音楽大学付属民族音楽研究所副所長。ピティナ(一般社団法人全日本ピアノ指導者協会)メディア委員。
講師:広上淳一教授(指揮)
インタビュアー:岡田敦子客員教授(ピアノ)
場所:C302教室(中目黒・代官山キャンパス)

東京生まれ。尾高惇忠にピアノと作曲を師事、音楽、音楽をすることを学ぶ。東京音楽大学指揮科卒業。1984年、26歳で「第1回キリル・コンドラシン国際青年指揮者コンクール」に優勝。以来、フランス国立管、ベルリン放送響、コンセルトヘボウ管、モントリオール響、イスラエル・フィル、ロンドン響、ウィーン響などメジャー・オーケストラへの客演を展開。これまでノールショピング響、リンブルク響、ロイヤル・リヴァプール・フィルのポストを歴任、このうちノールショピング響とは1994年に来日公演を実現、さらに米国ではコロンバス響音楽監督を務めヨーヨー・マ、五嶋みどりをはじめ素晴らしいソリストたちとともに数々の名演を残した。近年では、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ響、スイス・イタリア管、モンテカルロ・フィル、バルセロナ響、ビルバオ響、ポーランド国立放送響、スロヴェニア・フィル、サンクトペテルブルク・フィル、チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ、ラトビア国立響、ボルティモア響、シンシナティ響、ヴァンクーヴァー響、サンパウロ響、ニュージーランド響等へ客演。国内では全国各地のオーケストラはもとより、サイトウ・キネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団にもたびたび招かれ絶賛を博している。オペラ指揮の分野でもシドニー歌劇場デビューにおけるヴェルディ《仮面舞踏会》、《リゴレット》が高く評価されたのを皮切りに、グルック、モーツァルトからプッチーニ、さらにオスバルト・ゴリホフ《アイナダマール》の日本初演まで幅広いレパートリーで数々のプロダクションを成功に導いている。
2008年4月より京都市交響楽団常任指揮者を経て2014年4月より常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー、常任指揮者として13シーズン目の2020年4月より2022年3月まで京都市交響楽団第13代常任指揮者兼芸術顧問を務めた。2015年には同団とともにサントリー音楽賞を受賞。現在はオーケストラ・アンサンブル金沢アーティスティック・リーダー、日本フィルハーモニー交響楽団 フレンド・オブ・JPO(芸術顧問)、札幌交響楽団友情指揮者、京都市交響楽団 広上淳一。また、東京音楽大学指揮科教授として教育活動にも情熱を注いでいる。
2025年よりマレーシア・フィルハーモニー管弦楽団音楽監督に就任。
2024年第75回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

東京芸術大学付属高校、同大学を経て、同大学院博士課程(鍵盤領域)修了。スクリャービン(1872~1914)の演奏と論文によって、同大学の西洋音楽の分野で初めて博士号(学術博士)を取得。日本学術振興会特別研究員、東京芸術大学および沖縄県立芸術大学非常勤講師、京都市立芸術大学助教授を経て、2005年より東京音楽大学教授、2022年より副学長、現在客員教授。
演奏、教育、研究のみならず、評論活動も行い、ショパン没後150年記念国際シンポジウム(ワルシャワ)、スクリャービン生誕125周年記念国際音楽祭(モスクワ)などに招かれ、講演やリサイタルを行なう。校訂楽譜『スクリャービンピアノ曲全集』(全7巻、春秋社)はモスクワの国立スクリャービン博物館に所蔵されている。
講座に関するお問い合わせ先
寄付講座事務局
classic★tohmatsu.co.jp
★を@へ変換して送信してください
(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)
参考ページ