

大学院博士後期課程音楽専攻(作曲)
日本現代音楽協会主催 作曲コンクール
「第40回現音作曲新人賞」受賞
~探求テーマは”新しい伝統音楽観”~
中国からの留学生、魯 戴維さんは2023年12月21日に「第40回現音作曲新人賞」を受賞。
博士後期課程に在籍し、「現代日本と中国における琵琶創作の比較研究」をテーマに、“新しい伝統音楽観”を探求する魯さんに、受賞作品のこと、東京音楽大学での研究のことなどをうかがいました。
― 「第40回現音作曲新人賞」受賞おめでとうございます。今回応募した「日本現代音楽協会主催 作曲コンクール」と受賞作品についてお話をお聞かせください。
現音作曲新人賞は1984年に創設された新人作曲家のための作曲コンクールで、毎年異なるテーマで開催されます。今年のテーマは「現在形のデュオ」でした。私は元々、楽器の組み合わせにおける可能性に魅了されており、今回は最小限の室内楽編成である「デュオ」の可能性を試してみたいと考え、応募しました。作品のタイトルは≪エル・タンゴ≫といい、クラリネットとサクソフォーンがタンゴの踊り手として、時折お互いを模倣したり、同じ要素を演奏したり、ひとつの楽器のように音を重ねたりします。
このふたつの楽器を選んだ理由は、クラリネットとサクソフォーンが似た音色を持ちながらも、微妙に異なる点があるからです。これにより、作品の中で音色の可能性を広げることができると考えました。
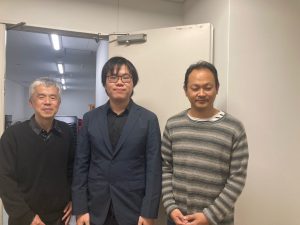
▲受賞作品を演奏してくださった菊地秀夫さん(クラリネット/左)、坂口大介さん(サクソフォーン/右)
― 作曲にあたって先生方からはどのような指導やアドヴァイスをいただいたのでしょうか?
主に記譜法と奏法に関してです。記譜法については、求める音響を楽譜に明確に伝える方法について、先生からさまざまなアドヴァイスをいただきました。奏法については、例えば自分が望む音響が選択した奏法で適切かどうか、またはより効果的な奏法が存在するかどうかについてコメントをいただきました。記譜と奏法は、作曲において非常に重要な要素だと思います。
― 魯さんは中国からの留学生として博士課程に在籍されていますね。
はい。昔から日本の音楽(現代音楽、伝統音楽、ゲーム音楽)が好きで、日本で音楽を学びたいと思っていました。特に、日本の作曲界と伝統音楽との関係や、日本から見た西洋音楽のあり方について知りたく、留学を志望しました。
―東京音楽大学大学院に進学を決めたのはなぜでしょうか?
東京音楽大学は、伝統音楽の演奏家として活躍する先生や音楽学の先生の層が厚いので、魅力を感じました。以前から細川俊夫先生の作品に興味があり、細川先生のもとで学びたいと思い、東京音楽大学を志望しました。
来日以前は、中国の高校を卒業後、アメリカに留学しています。日本とアメリカの最も大きな違いは、日本では作曲だけでなく、作曲を学ぶ学生が研究することも重視されていると感じますね。音楽の歴史や社会的文脈について興味を持つ人にとって、よい環境ではないでしょうか。
また、作品が演奏される機会も多く、非常にありがたく思います。
― 博士課程ではどのような研究に取り組んでいますか?
現在研究しているテーマは「現代日本と中国における琵琶創作の比較研究」です。さまざまな文化における琵琶という伝統音楽の取り入れ方を研究し、さらに世界中の民族楽器を現代楽器として扱い、協演を促進することを目指しています。琵琶は古くは西アジアから伝わり、日本と中国の両国で国際的な楽器と見なされていました。しかし、中世以降はそれぞれの国の芸能と美学と融合し、各地域の独自の楽器へと進化しました。そのため、現在では日本と中国の琵琶は全く異なる方向に発展しています。これら異なる方向に進化した楽器を一緒に演奏することで、私は文化の交流を感じることができます。
したがって、私が最も興味を持つ作曲テーマは「新しい伝統音楽観」です。これまでにふれてきた伝統音楽が現代においてどのように変容し、どのように再定義されるかについて、探求しています。
― 魯さんの作品にもそのテーマがあらわれているのでしょうか?
そうですね。このコンクールのために作曲した≪エル・タンゴ≫もその一例です。「タンゴ」という広く知られた音楽ジャンルから、理論的にその要素を抽出し、ジャンルの象徴的な意味だけを用いて作品を構築する、いわゆる「脱構築」的なアプローチを試みました。
― そのような魯さんの創作活動を見守ってくださる先生方の、日頃のレッスンについても教えてください。
私のレッスン担当教員は、主には原田敬子先生と野平一郎先生です。東京音楽大学での先生方とのレッスンはとても楽しい時間です。創作に関する意見はもちろんのこと、将来の方向性や作曲家としての指針についてもご指導いただいています。先生方のおかげで、創作と成長の目標を見つけ、技術だけでなく、より自分らしい考え方(例えば文化の融合など)で作品を書くことを決意しました。
また、これからはエレクトロニクスについても学びたく、有馬純寿先生のもとで勉強する予定です。東京音楽大学の先生方は幅広い分野に精通しており、そのおかげで多くのことを吸収することができました。
― エレクトロニクスも!さまざまな専門分野の教員が在籍しているのも、本学の魅力のひとつですよね。学生生活はいかがですか?
クラスメートも皆さん親切な方ばかりです。この大学では国籍や文化、興味のバリアをほとんど感じずに交流や学びができるので、安心して過ごすことができます。
― 最後に、東京音楽大学のよいところを自由にどうぞ!
練習室とホールの設備が非常に優れていることですね!練習室は数も多く、楽器や機材のクオリティーも高いと感じます。また、2024年2月に開催された私の博士リサイタルでは、ピアノソロ、チェロソロ、ギターソロ、薩摩琵琶ソロの作品がTCMホールで演奏されました。それぞれの楽器の響きが非常によく、楽器の特性をホールによって発揮することができました。おかげさまで、すばらしい演奏と録音を行うことができました。
学生食堂の料理も美味しくて、毎回ふたつセットを注文しています!
(総務広報課)
参考ページ